このページでは、かだ由紀子の著書一覧をごらんになれます。著書は以下のように分類してあります。
著書一覧
『子どもは誰のものか? 離婚後「共同親権」が日本を救う』(2025年)
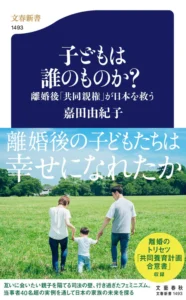
文藝春秋
国際的に離婚後の共同親権が認められるなか、なぜ日本では“骨抜き”の共同親権しか実現し得ないのか。全国四〇人超の当事者との対話を通して浮かび上がったのは、行き過ぎたフェミニズムがもたらした社会の歪みだった。「子どもの最善の利益」を第一に考えた、日本の家族の未来を展望する。
『政治家を目指す女性たちへ』(2023年)

田村重信編/内外出版
統一地方選挙に役立つ! 非公開セミナー講演録!二階俊博、下村博文、行徳哲男、鈴木貴子、大下英治、デービッド・アトキンソン、田村重信と共著
『水と生きる地域の力 琵琶湖・太湖の比較から』(2022年)
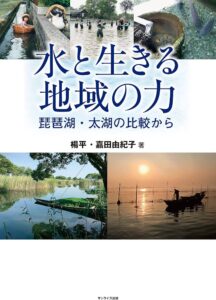
楊平と共著/サンライズ出版
「人類のコミュニティは水場からはじまった──水道の普及で私たちはそのことを忘れはじめているにすぎない。日本と中国で水と共にある暮らしを緻密に踏査した地域社会学者の提言の書。」早稲田大学名誉教授・元日本社会学会会長鳥越皓之氏推薦! 日本の琵琶湖辺と中国の太湖周辺において、水辺のエコトーンを活用し、いかに稲作、漁撈、養魚、養蚕などの生業が複合的かつ合理的に実践されてきたかを紹介。地球規模の環境問題と気候変動が拡大するいま、改めてコミュニティ主義の有効性を問う。
『流域治水がひらく川と人との関係』(2021年)
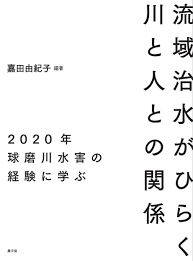
農山漁村文化協会
2020年7月4日九州で球磨川水害が発生し、50名もの方が亡くなった。この人たちはなぜ・どのようにして亡くなったのか。研究者と被災者たちによる共同調査から明らかにする。また2021年4月流域治水関連法が成立。国の治水方針の大転換であるが、本書は流域治水の歴史と意義、その可能性について詳述している。亡くなられた一人ひとりに目を向けた、それも被災当事者を交えた調査のとりまとめとしても、流域治水の総合的な解説書としてもはじめてのもの。2020年球磨川水害の経験に学び、気候危機の時代に求められる流域治水を展望する。
『命をつなぐ政治を求めて 人口減少・災害多発時代に対する〈新しい答え〉』(2019年)
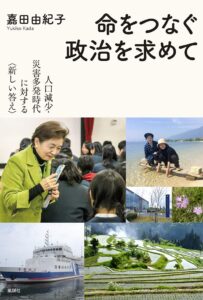
風媒社
まずは、議論を積み上げよう!後追い型ではなく「事前対応型」の政策を滋賀県政で実行してきた著者による人口・格差・経済・災害問題に挑むこれからの政治への新しい提案。
『博物館資料保存論〔新訂〕』(2019年)

稲村哲也・本田光子/放送大学教育振興会
博物館資料である「もの」の保存について、その考え方を理解し、知識を学び、技術に触れる。「もの」の保存は、材質や製作技法など資料の特徴を捉え、伝えてきた人や時代の判断を知り、「もの」に適した環境を整え、必要に応じて繕うことにより成り立つことを理解する。また、具体的事例を参照し、その意義や方法について包括的に学ぶ。さらに、防災、危機管理、伝統・環境の保全など、地域との連携についても理解し、今後の資料保存について考える。
『滋賀県発!持続可能社会への挑戦 科学と政策をつなぐ』(2018年)
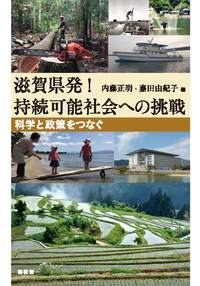
内藤正明と共編/昭和堂
「琵琶湖が死の湖に!」それは1977年、大型赤潮発生から始まった。原因究明から対策立案、そして住民を巻き込んだ「せっけん運動」から「富栄養化防止条例」制定へ。こうした科学と政策の連携プレーで次々と先進的環境政策を推進した滋賀県。その理念と歴史を紐解き原動力に迫る。最新の「滋賀モデル」の構築と、原発事故を想定した放射性物質拡散シミュレーションもくわしく紹介。
『女は「政治」に向かないの?』(2018年)

秋山訓子著/講談社
「女性活躍」が叫ばれる一方で、女性は未だ政治から遠い位置にある。野田聖子、小池百合子ら彼女たちは、なぜ政治を志し、どう壁を打ち破っていったのか。そして、女性が自分らしさを殺さずに、超・男性社会で生き抜いていくためにはどうすればいいのか。政治記者が見聞きした、女性政治家の本音と女の人生の泳ぎ方。
『レイチェル・カーソンに学ぶ現代環境論 アクティブ・ラーニングによる環境教育の試み』(2017年)

新川達郎・村上紗央里と共編/法律文化社
カーソンのアイデアに学びつつ、自分自身の感性や関心に立脚して環境問題を考えるための教育実践を書籍化。
『子どもたちの生きるアフリカ』(2017年)
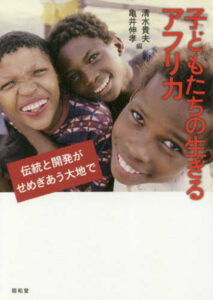
清水貴夫・亀井伸孝編/昭和堂
〈自然×文化〉〈伝統×開発〉が織りなす環境で、遊び、働き、学ぶ。今この瞬間にも、あの広大な大地でアフリカの新世代が育っている
『いのちにこだわる政治をしよう!』(2013年)
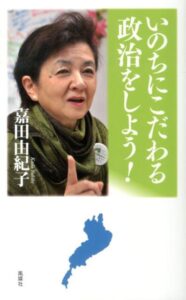
風媒社
なぜ希望なき政治を選ぶのか。今すぐ原発をゼロに。エネルギーを市民の手に。著者のバックボーンや信条、滋賀県知事としての実践を紹介し、あらためて地方から国を変えるための自治の実践についてまとめた。
『若手知事・市長が政治を変える(1) 未来政治塾講義』(2013年)
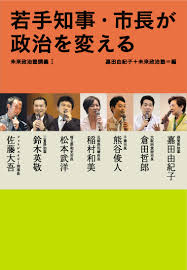
未来政治塾と共編/学芸出版社
日本の未来を拓く政治の担い手を育てることを目的に、滋賀県の嘉田由紀子知事が2012年に立ち上げた「未来政治塾」。若者や女性を中心に670名が受講した人気講義を書籍化。全国最年少知事をはじめ30代、40代知事・市長が挑戦する未来に責任をもてる政治とは。日本の政治のしくみを変えていく革新者たちの講義録
『地方から政治を変える(2) 未来政治塾講義』(2013年)

未来政治塾と共編/学芸出版社
日本の未来を拓く政治の担い手を育てることを目的に、滋賀県の嘉田由紀子知事が2012年に立ち上げた「未来政治塾」。若者や女性を中心に670名が受講した人気講義を書籍化。日本の政治のしくみを変える革新者たちの講議録。
『知事は何ができるのか 「日本病」の治療は地域から』(2012年)
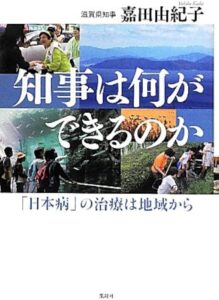
風媒社
新幹線新駅建設やダム建設などの見直し、原発再稼働問題など、生活者目線を失わず、筋道を通す政治を力強く実行してきた現役知事による闘いの軌跡。日本の政治の未来を憂う誠意ある政治家、公務員、そして日本社会のリーダー必読の書。
『生活環境主義でいこう! 琵琶湖に恋した知事』(2008年)
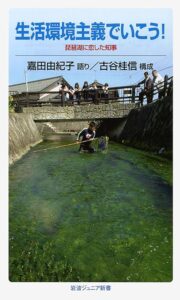
古谷 桂信編/岩波書店
滋賀県知事として活躍する嘉田が,長く環境社会学者としてたずさわってきた琵琶湖の研究をもとに語る環境社会論.近代技術主義にとらわれず,昔ながらの水利用の知恵に学ぶ自然との関わり方とは?人々の暮らしの視点に立ち自然環境と社会生活との共存を目指す新たな地域づくりのあり方を提案。
『水・環境・アジア グローバル化時代の公共性へ』(2007年)
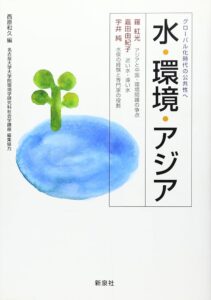
羅紅光・宇井純と共著/新泉社
グローバルに広がる環境問題の解決に向けて、水俣・琵琶湖・メコン川での取り組みから、これからの公共的・実践的アプローチを提案。
『琵琶湖博物館を語る 対談 』(2007年)
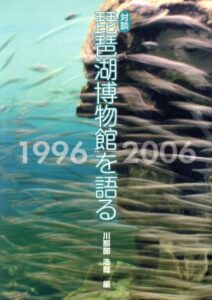
川那部浩哉編/サンライズ出版
琵琶湖の自然と文化、沖島の漁業の変遷
『里川の可能性 利水・治水・守水を共有する』(2006年)
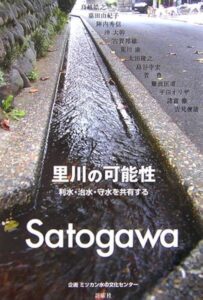
鳥越皓之 陣内秀信 沖大幹 ほかと共編/新曜社
里川とは里山をもじった造語。故郷の小川のイメージだけでなく、都会の川、街中の水路なども広く含む。環境社会学・建築史・河川工学の視点から、日本中の川を三面コンクリートにした河川行政の行き過ぎを反省し、琵琶湖、熊本、愛知、山梨、東京下町などで川と人の深い結びつきを調査・取材。飲料水や農工業など経済目的の利水、水害の被害を防ぐ治水だけでなく、川を地域の財産、愛着ある場として共有する「守水」の考え方を「里川宣言」として提案している。
『私たちの「いい川・いい川づくり」最前線』(2004年)

「いい川 いい川づくり」研究会/学芸出版社
500団体、延べ2500人が参加し、川と川づくりの新しいあり方を発見する「川の日」ワークショップの実践レポート。河川法改正を機に、河川管理者側と市民組織が連携し、市民が育てる「いい川」、行政が取組む「いい川づくり」の活動が展開されている。市民・行政・専門家がソフト・ハードの別を越えた川づくりの現況と展望を示す。
『水をめぐる人と自然──日本と世界の現場から──』(2003年)

有斐閣
水問題は絶対的な水量の不足、水の汚染問題とあわせて、公正な社会的配分の問題や地域固有の生態系や文化の保全とも深くかかわっている。日本と世界の水問題の現場で活躍する研究者やNGO十名の著者が、その現状を報告するとともに、将来への展望を模索する。全体の企画、編集とともに琵琶湖・淀川水系の上下水道100年の歴史を公共性のくみたてという論点からたどる。
『水と暮らしの環境文化──京都から世界へつなぐ──』(2003年)

槌田たかし・嘉田由紀子編/昭和堂
1200年の京都の歴史をささえてきたのは清浄なる水だと言っても過言でないほど、京都の生態と文化を考える上で、川、地下水の果たした役割は大きい。京都の水文化を酒や庭園、近代の琵琶湖疏水とからめてたどりながら、逆に水の不足する世界の乾燥地帯での水問題を対比させることで、その特筆を描き出した。槌田とともに全体の企画、編集とともに、水所有の文化的意味「近い水、遠い水」を執筆。
『弥生のなりわいと琵琶湖──近江の稲作漁労民──』(2003年)
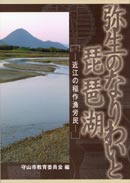
守山市教育委員会編/サンライズ出版
田んぼは稲をつくるだけでなく、魚も育てた。特に大きな河川や湖沼周辺の湿地帯では、自然の水の増大にあわせて、田んぼに魚がはいった。水陸どちらにでも適応しながら、融通のある生業を育ててきた琵琶湖辺の暮らしは、ある意味、弥生時代の精神文化を表現しているといえないか。今と昔をつなぐそんな思いから守山市が企画したシンポジウムの記録である。「琵琶湖のほとりの生活史──環境社会学の立場から──」を執筆するとともに全体討論の進行をする。
『聞き書き 里山に生きる』(2003年)

徳岡治男語り、小坂育子構成/サンライズ出版
琵琶湖をのぞむ比良山の麓に栗原という美しい集落がある。そこに70年以上生きてきた徳岡さんの山里の暮らしに彩られた心の機微を、水田づくり、水利と祭の仕組み、そして家族の歴史とともに描く。小坂さんの精魂こめた聞き取りが、多くの図や写真とともに、里山の暮らしを見事によみがえらせた。「里山にいきる“わきまえ”」を、はしがきとして寄せる。
『環境社会学』(2002年)

環境学入門シリーズ/岩波書店
環境は人の社会や精神とどうかかわっているのか、日常生活をなりたたせている、水、食物、住居、遊び、など、身近な素材を切り口に、モノ、コト、ココロのまるごと環境社会学としてまとめる。キーワードには、水や生活環境問題にかかわるポイントをまとめる。
『現代アフリカの社会変動ーことばと文化の動態観察』(2002年)

宮本正興、松田素二編/人文書院
混沌として混迷をきわめるかにみえるアフリカ社会がいかに20世紀の植民地支配の影響を払拭しえないでいるか、ポストコロニアルアフリカの現状と将来を人類学、社会学などの人びとが現地からの息吹をもとにつたえる。嘉田は、中山節子、ローレンス・マレカノとともに、「ムブナはおしくない?-アフリカ・マラウイ湖の魚食文化と環境問題」を執筆。
『エスノグラフィー・ガイドブックー現代世界を複眼でみる』(2002年)

松田素二・川田牧人編/嵯峨野書院
文化人類学の基本的手法としての「エスのグラフィー(民族誌)」の手法であらわされた各種の研究書を分担で書評をし、その現代的活用を考えた書。嘉田は石牟礼道子の「苦海浄土」と菊池武雄の「自分たちで生命を守った村」の書評を分担。
『水辺ぐらしの環境学ー琵琶湖と世界の湖からー』(2001年)

昭和堂出版
人はなぜ水辺にひかれるのか?琵琶湖の徹底したフィールドワークでの日本人の水辺とのかかわりの記録を足場に、アフリカのマラウイ湖、スイスのレマン湖、中国の太湖、アメリカのメンドータ湖など世界の湖へでかける。そこで発見したものは?
『今昔写真でみる世界の湖沼の100年』(2001年)

(財)国際湖沼環境委員会、滋賀県立琵琶湖博物館の共同編集
フランスのセーヌ川、スイスのレマン湖、アメリカのメンドータ湖、アフリカのマラウイ湖など世界の湖沼の過去100年の変化を同じ場所・同じアングルで写す今昔写真で比較。世界的には、暮らしが水辺から離れ、水辺が車に占拠されてきたという共通の変化をみることできる。嘉田は全体の企画と調査、編集を担当。ここでの写真のすべては、琵琶湖博物館のHPで、日本語、英語、フランス語、ドイツ語で見ることできる。
『知ってますか この湖をーびわ湖を語る50章』(2001年)

琵琶湖百科編集委員会編/サンライズ出版
世界湖沼会議にあわせて、琵琶湖の歴史、文化、自然のまるごと最前線をまとめた書。ともすれば水ガメ、あるいは水汚染の場として認識されている琵琶湖が、数百万年の歴史をもつ古代湖であり、縄文弥生の時代からの湖沼文化を継承する湖であることもあわせて示す。英文のアブストラクトをつけて、海外むけの利用もはかる。嘉田は全体企画と編集を担当。
『増補改訂版 世界の湖』(2001年)
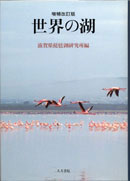
吉良竜夫・中村正久編著/人文書院
五大陸58の湖の現状と歴史、湖畔のくらし、問題点と対策を研究者の目でつづったもの。水の汚染、環境変化の歴史など多面的な湖の意味をさぐる。嘉田は「マラウイ湖」を担当。
『施策としての博物館の実践的評価ー琵琶湖博物館の経済的・文化的・社会的効果の研究』(2001年)

村山皓編/雄山閣
1996年に一般公開した琵琶湖博物館の文化施設としての効果を、システムダイナミックスや、地域アンケートの手法を活用して評価してまとめたもの。琵琶湖博物館と立命館大学政策科学部との共同研究の成果。嘉田は9章「地域社会での博物館利用の実践的展開の可能性ー琵琶湖博物館の来館が県民にもたらす博物館イメージから何が展望できるか」を分担執筆。
『環境社会学ー自然環境と環境文化』(2001年)

鳥越皓之編/有斐閣
人間の生活を出発点に自然と文化を再考した論文集。嘉田は橋本道範と共著で「漁労と環境保全ー琵琶湖の殺生禁断と漁業権をめぐる心性の歴史からー」を執筆。
『日本の水文化ー水をいかした暮らしとまちづくり』(2001年)
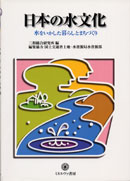
三和総合研究所編、編集協力・国土交通省土地・水資源局水資源部/ミネルヴァ書房
水の歴史的、文化的、地域個性をあらためて生かした地域づくりのための提案書。水資源部の委員会記録を現場での実践記録とともにまとめたもの。嘉田は第1章「水文化って何?」を担当。
『たんけん・はっけん・ほっとけん──子どもと歩いた琵琶湖・水の郷のくらしと文化──』(2001年)
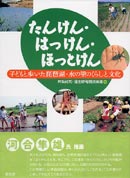
井阪尚司・蒲生野考現倶楽部編著/昭和堂
地域や環境学習をすすめるための一般向きスローガンの感さえある「たんけん・はっけん・ほっとけん」。この考え方はいつどのようないきさつから生まれたのか。1980年代末から90年代末の10年の活動記録を推進する教員と地域の人たちがまとめたもの。嘉田は全体プログラムの企画にかかわるとともに、まとめの座談会の進行とあとがきを執筆。
『生活―環境革命 別冊「環」3』(2001年)
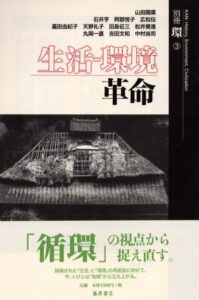
山田国広・石井亨・阿部悦子他/藤原書店
「循環」の視点から捉え直す。近代の科学技術文明が提供し、先進国の人々が享受してきた快適さ、便利さへの代償として、物理的な自然環境の破壊とともに、自然と固く結びつき、人間の文化を育んできた日々の生活そのものが破壊されている。単純に過去の状態に戻ることが困難をきわめる今、破壊が極限まで達しつつある「生活」と「環境」を再創造することは可能か。
『水辺遊びの生態学ー琵琶湖地域の三世代の語りから』(2000年)
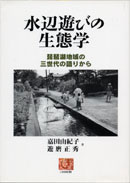
遊磨正秀と共著/農山漁村文化協会
「よい子は川で遊ばない」という標語がいつのまにかひろまった日本。今の子どもたちの父母や祖父母の時代、川や池や水田は子どもたちの遊び場であり、おかず確保の場だった。その時代の生態と社会的仕組みを6000人の人びとへの聞き取りとアンケート調査から再現し、水辺に子どもたちをとりもどす方向を模索する。
『生活再現の応用展示学的研究ー博物館のエスノグラフィーとしてー』(2000年)

古川彰と共編/琵琶湖博物館研究調査報告、第16号、滋賀県立琵琶湖博物館発行
昭和30年代、川や湖の水を直接生活につかっていた時代、人間の屎尿も、大便と小便をあらかじめ分離して「養い水」とし、農業用の肥料につかっていた。その時代の生活と生産の仕組みをまるごと再現した琵琶湖博物館展示の背景資料とその制作プロセス、開館後の来館者の反応などをまとめたもの。
『みんなでホタルダスー琵琶湖地域の水とホタルの再生』(2000年)
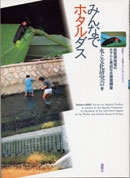
水と文化研究会編集/新曜社
1989年から琵琶湖周辺で、川や水辺と人びとのかかわりを近づけることを期待してはじめに「ホタルダス(住民参加のホタル調査)」の10年間の記録を、生息状況、生息場、参加者の意識、社会論などからまとめた書。嘉田は全体企画と編集を担当。
『共感する環境学ー地域の人びとに学ぶ』(2000年)
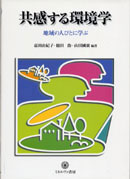
槌田劭、山田國廣と共編/ミネルヴァ書房
京都精華大学環境社会学科の開設にあたり、関係する教員が新入生にむけて自己紹介をかねて執筆した書。環境を考えるためには、生きる現実から離れず理解し、行動するための、実践の書をめざす。
『農山漁村と生物多様性』(2000年)

宇田川武俊編、農林水産技術情報協会監修/家の光協会
農山漁村の生態系における生物と人間活動とのかかわりを生態学、土木工学、社会学、民俗学などの立場から考える。嘉田は8章「生物多様性と文化の多様性ー水辺環境の実践的保全論にむけて」を執筆。
『博物館を楽しむー琵琶湖博物館ものがたり』(2000年)

川那部浩哉編/岩波書店
琵琶湖博物館の開館準備から開館直後の運営の課題、将来の方向を直接にかかわった学芸員、展示業者、建築家などが共同執筆したもの。嘉田は、「蛇口のない時代の人びとのくらしと環境ーC展示室」(布谷と共著)、と「世界の湖、世界の博物館と連携して」を分担。
『ミュージアムの思想──小林達雄対談集』(1999年)
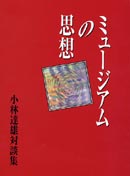
株式会社ミュゼ発行
縄文時代を語るには小林さんの右にでる人はいないといわれる、その小林さんが博物館づくりに執念をかたむける人と交わした対談集。嘉田は、琵琶湖博物館の企画・運営にかかわる経験から、「必要条件としての住民参加」について、討議。
『琵琶湖・淀川水系における水利用の歴史的変遷』(1998年)

小笠原俊明と共著/琵琶湖博物館研究調査報告、第6号滋賀県立琵琶湖博物館発行
「琵琶湖の水は1400万人の飲料水になっている」と一般にいわれているが、いつからなぜ、それほどたくさんの人たちが琵琶湖水源に依存するようになったのか、まとまった資料は皆無だった。琵琶湖博物館の開館にあたり、その歴史的変遷を近畿圏の土地利用、行政区域の変遷とあわせてたどる。明治28年、大正2年、昭和10年、昭和30年、昭和50年、平成4年とほぼ20年ずつの地理的変遷と量的拡大を把握した。嘉田は全体企画と編集・執筆を担当。
『環境アセスメント ここが変わる』(1998年)

「環境アセスメントここが変わる」編集委員会編/環境技術研究協会編
環境アセスメント制度の発足にかかわって、その現状と将来の展望をさまざまな立場から実践的に論じた書。嘉田は「自然文化環境の評価への試み」を遊磨と共著。
『私とあなたの琵琶湖アルバムー琵琶湖博物館開館記念1周年企画展』(1997年)

小笠原俊明と共同編集/滋賀県立琵琶湖博物館発行
昭和30年代を境に急速にかわった琵琶湖と滋賀県の生活風景を、同じ場所・同じアングルからの今昔写真でたどる企画展示の図録。「華やかな水」「暮らしの水」「なりわいの水」「子どもと水」「災いの水」「変わりゆく水」として分類、画像データベースの手法なども紹介。嘉田は全体企画と「写真が語る環境の変遷」文と編集を担当。
『水辺の遊びにみる生物の時代変遷と意識変化──住民参加による三世代調査報告書』(1997年)

遊磨正秀・藤岡康弘と共著/琵琶湖博物館研究調査報告、第9号、滋賀県立琵琶湖博物館発行
「昔はここで魚つかみをしたのに」とさびしそうにコンクリートになった水路をみるおじいちゃんたち。あっというまに20や30種類の魚の名前を思いだしてくれる。この「記憶を記録に」という思いから地域の人たちと編み出した手法で昔の子どもたちの生き物遊びを発掘、再現。1992年から96年まで滋賀県内2000人の子どもたちが自分たちの父母、祖父母に聞き取りをして合計6000人の3世代比較も行う。2000年に出版した本の元資料である。
『滋賀の自然と人を語るー新しい淡海文化の創造をめざしてー』(1997年)

淡海文化図書編集会議編/ぎょうせい
琵琶湖を淡海とよびならしてきた人たちがはぐくんできた歴史と文化にもういちど現代の目をそそぐ、という趣旨からはじまった淡海文化創造の政策。その一環として企画された書。全体が「自然」「人間」「生きる」の3部構成となっており、嘉田は「人間」の構成の企画と司会・編集、全体のまとめ会議の司会を担当。
『川・池・湖・海 自然の再生 21世紀への視点』(1996年)

日本村落研究学会編/農山漁村文化協会
「村落社会研究は環境問題にどうアプローチできるか」を課題にひらかれた学会報告のまとめの書。共有資源問題や持続性理論の重要性がここで指摘され、個別の調査報告のつなぎとなった。嘉田は問題提起論文を執筆するとともに全体企画と編集を担当。
『琵琶湖・水物語──湖国の絆は時代<とき>をこえて──』(1996年)
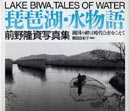
前野隆資写真・嘉田由紀子解説/平凡社
湖畔の洗い場の1枚の写真がとりもってくれた前野隆資さんとのおつきあい。昭和5年から60年以上にわたり、カメラを日記がわりに湖国をうつしつづけた前野さんの8万コマにわたる写真の1枚1枚の撮影場所、撮影内容を伺いながら昭和30年代への思いをはせたひとときは、調査者冥利につきる時間だった。その中から100枚をえりすぐり、湖国の昭和30年代を伝える。
『湖人 琵琶湖とくらしの物語』(1996年)
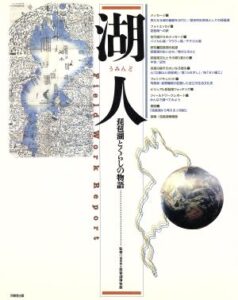
滋賀県立琵琶湖博物館開館記念誌編集委員会
琵琶湖の自然、歴史、人々との生活との係わりとその変容を広い視野から見つめ、琵琶湖とのよりよい共存関係を築いていくことを考える。10月に開館する琵琶湖博物館の概要と研究・展示の指針を伝える。
『生活世界の環境学ー琵琶湖からのメッセージ』(1995年)

農山漁村文化協会
「ホタルがすきなら蚊はがまんしよう」。自然と人とのかかわりは「ええとこどりはできない」という琵琶湖辺の村人の言葉にうごかされ、地域をあるき、水と人のかかわりを地元教師に教えてもらいながら発見したかずかずのできごとから「生活環境主義」の心髄を伝える。
『森の教室ー生きもの賛歌ー』(1995年)

久山喜久雄編/淡交社
京都東山に法然院というお寺があり、その境内に「共生き堂」という小さなお堂がある。1985年以来、このお堂を舞台に「森の教室」がひらかれてきた。この書はその講師たちの声をあつめたもの。嘉田は「水と暮らし」について、昭和30年代の水道以前の水利用についてまとめた。
『地球に生きるー環境の社会化』(1994年)

掛合誠編/雄山閣
グローバルな視点から人類と環境のありかたを問い直し、自然と文化の新しいパラダイムを提示した論文集。嘉田は「水汚染をめぐる科学知と生活知」を担当。
『試みとしての環境民俗学ー琵琶湖のフィールドから』(1994年)

鳥越皓之編/雄山閣
人間の手が加わった環境を考えるときに、いかに人が周囲の環境を認識し、そこにいかなる手をくわえることで、いかなるちがいがうまれるのか、民俗学と社会学のものたちによる論文集。嘉田は「水と生活の民俗伝承」を執筆。
『環境社会学』(1993年)

飯島伸子編/有斐閣
1992年に環境社会学会が発足してはじめてのまとまった教科書。被害構造論、社会的ジレンマ論、生活環境主義など、環境社会学の主要な論点がここででそろう。嘉田は第7章「環境問題と生活文化ー水環境汚染を手がかりとして」を担当。
『シロウトサイエンスのサイエンス』(1992年)

第10回、琵琶湖研究シンポジウム記録、琵琶湖研究所
1989年から1992年まで3年間続けて、住民参加による環境調査のまとめ報告書。「夏はホタル、冬は雪」という蛍雪作戦の環境調査のはじまりから展開を、当事者の視点から発言し、まとめたもの。参加型環境調査のさきがけといえる。
『水と人の環境史ー琵琶湖報告書』(1992年)

鳥越皓之と共編、増補版、初版1984年/御茶の水書房
「そこにも人は住まねばならない」。環境問題を近代技術の問題や、自然保護の問題と考える傾向にあった1980年代、それは人と自然のかかわりの社会的、歴史的、文化的問題であり、その構造がもっとも見えやすいのは「生活現場」であることを提起した書。
『湖の国の歴史を読む』(1992年)

渡辺誠編/新人物往来社
琵琶湖をめぐる水と人間の歴史を歴史学、社会学のたちばから論じたもの。嘉田は「水と人びとのくらし」を分担執筆。
『環境イメージ論──人間環境の重層的風景』(1992年)
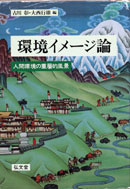
古川彰・大西行雄編
環境問題を、風景という切り口からとらえた書。嘉田は長浜の風景の変遷と、ホタルと日本人のかかわりについて論述。
『環境イメージ論──人間環境の重層的風景』(1992年)

野村雅一編/ドメス出版
日本人の情報リテラシーが急速に進展した戦後の社会史を文化人類学、社会学、民俗学などの分野から分析した論文集。国立民族学博物館の共同研究の成果でもある。嘉田は大西行雄と共著で「野外調査と電縁ネットワーク:パソコン通信による地域情報の発信と咀嚼」として、当時開始したパソコン通信の掲示板機能を活用した「夏はホタル、冬は雪」という住民参加型調査の理念と実践について執筆。
『現代日本の構造変動──1970年以降』(1991年)

遠藤惣一・光吉利之・中田実編/世界思想社
産業・政治・地域・家族・生活構造・階層など社会学が扱う各領域において、近年どのような社会変動がおきたのか、その分析書。嘉田は生活構造の変化を「水の社会化をめぐって」として分担執筆。
『人間にとって農業とは』(1989年)
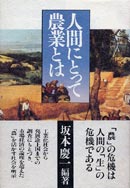
坂本慶一編著/学陽書房
工業化社会から発展途上国までの現地調査に基づき、市場経済の論理をこえた「農」の思想と実践を活かす社会を見通した書。嘉田は「水の災いをめぐる村人の記憶と語り」として、琵琶湖岸の村での水害被害の語られ方を分析しながら、「ええとこどり」はできなかった災害思想を描写。
論文/レポート等一覧
『三世代交流型調査検討業務報告書(概要版)』(2004年)

子ども流域文化研究所
『私たちの水 身近な水環境調査』(2002年~2007年、第一号~第五号まで)
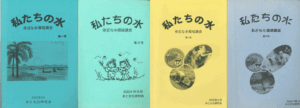
水と文化研究会
『世界子ども水フォーラム』(2002年)

世界子ども水フォーラム実行委員会準備会事務局・湖沼会議市民ネット
『蒲生町の人と水』(1993年、1994年)
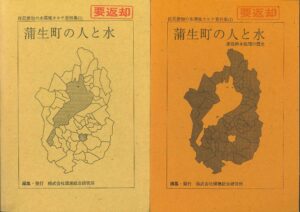
株式会社環境総合研究所
『コミュニティ水環境カルテの作成』(1993年)

株式会社環境総合研究所
『琵琶湖博物館情報システムの開発に関する設計』(1993年)

株式会社CRC総合研究所
『雪んこの気象日誌』(1990年~1993年、1巻~3巻)
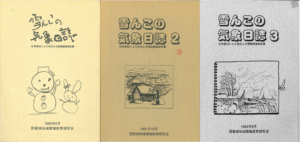
琵琶湖地域環境教育研究会
『琵琶湖研究所委託研究報告書』(1990年、1991年)
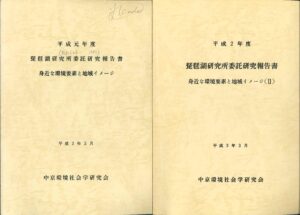
中京環境社会学研究会
『私たちのホタル』(1989年~1990年、第1号~第10号)
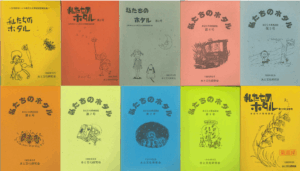
水と文化研究会
『環境認識と風景感に関する文化論的アプローチ』(1987年~1988年)

中京環境社会学研究会
『環境問題への文化論的・視覚的アプローチ』(1987年~1988年)
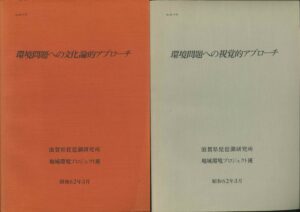
滋賀県琵琶湖研究所 地域環境プロジェクト班
『滋賀県地域環境アトラス』(1986年、1988年)
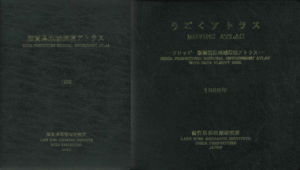
滋賀県琵琶湖研究所
『琵琶湖地域環境教育研究会の記録』(1983年、1989年)
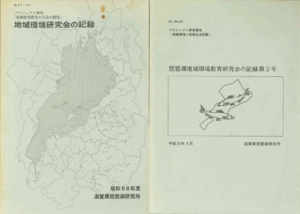
滋賀県琵琶湖研究所
