9月6日・7日と泊まりがけで、神戸で開かれた「水の環フォーラムin神戸―山から海へ、過去から未来へと繋ぐ 人と水の環―」に参加。今回の会合への参加はふたつの思いがあります。ひとつは、1980年代初頭に「雨水は宝」と雨水を集め・ためて、洪水を防ぎ、同時に日常的に貯めた水を暮らしに使う運動をはじめた村瀬誠さんの挑戦が今どうひろがっているかこの目で確かめたかったからです。あれから40年です。今私たちが追跡している「近い水」に根ざした流域治水や水循環社会づくりとつながっています。もうひとつは、この広がりを担っているのはどうも造園などお庭づくりの女性たちらしい、それもグリーンインフラを表明しておられる。この6月に水俣で開催された球磨川流域圏会議で実行委員長の法貴弥貴さんからお誘いを受けてにぎやかで楽しそうとでかけました。全国から200名もの参加者、ポスターセッションも40組!!緑の流域治水の10年プロジェクトリーダーの島谷幸宏さんや国立環境研究所の西廣淳さん、東大の蔵治光一郎さんなど現役の研究者ともじっくりお話できました。また2000年代初頭から各地にできた流域委員会のひとつで、武庫川水系流域委員会で活躍しておられた松本誠さんとも久方ぶりにお会いしました。9月9日。1500文字。
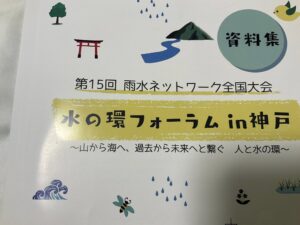


実行委員会の法貴弥貴さんは、「造園女子4人組」の「グリーンインフラ市民学会」の会長で、栗原薫さん、来島由美さん、松下美香さんと実行委員会を引っ張ってこられました。山から海までの水循環、雨水の利用など、全国各地で活動している方々と直接お会いでき、まさに市民主体の活動ばかり。それと造園などインフラづくりにここまで女性が関わっていること、改めて感動しました。皆さん子育て経験の中から、「近い水」「近い緑」の価値を発見なさっておられます。
またディスカッションでは、兵庫県立大学准教授の「合意形成学」を専門とする高田知紀さんがモデレーターとなり、「やってみたいこと」をまず個人的に提案し、それをどうやったら実現できるのか、グループディスカッションを行うという趣向。市民・専門家・企業・行政と立場を超えての意見の違いを超える方法を実践。議論の後の皆さんのお顔が充実しており、皆さん満足そうでした。夜の交流会も発酵食を主に、手作り料理で満足。





交流会の最後に挨拶時間をいただいたので二つのことをお伝えしました。ひとつは、水と住民活動に50年近くかかわってきたが、今日のこの会合は村瀬さんたちが蒔かれた種が見事に芽をだし花を咲かせてくれていることに感動したこと。特にインフラづくりに女性がたくさんかかわっていることが素晴らしいと。もうひとつは、国では10年以上前に水循環基本法ができ専門の担当部局もできたが、自分が国会議員となって国の動きを見ているが、まだまだ政治の世界で定着できていないこと。特に高度経済成長時代に形成された「中央集権型」「一局集中型」の「遠い水」社会ではなく、「多極分散型」「オンサイト立地型」の「近い水」の動きが今こそ必要であり、それが各地で実践されていることを教えていただき、「遠い水」から「近い水」へという原点を国政でも展開していきたい、と伝えました。
翌日のエクスカーションでは、私は「水みちから神社をめぐる」というプログラムに参加。垂水(たるみ)の地元住民の高田知起さんが垂水の街中を、大正時代の地図を片手に、いかに「垂れる水」つまり「瀧」が、コンクリートで固められた町中で痕跡が見えるかを案内下さいました。崖の上につくられた住宅の石積みの間からかすかに流れる浸みだし水、その水が集まる水路に生きるサワガニ。住宅のブロック積みの間から浸みだし水をバケツにためて「すきま緑」を育てている住宅など、今も活きる「近い水」発見に感動でした。高田さん、丁寧なご案内、ありがとうございました。






